『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』 想田和弘
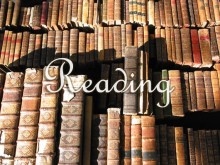
瞬間と向き合い観察すること、瞬間を受け入れて生きること
想田和弘監督の前の著書『精神病とモザイク タブーの世界にカメラを向ける』では、観察映画第2弾となる『精神』(2008)誕生の背景や作品に対する様々な反応が綴られていた。新しい著書『なぜ僕はドキュメンタリーを撮るのか』では、現在公開中の観察映画最新作『Peace』(2010)の製作過程を振り返りつつ、「ドキュメンタリーとは何か」というテーマが掘り下げられていく。
しかし、本書のなかでその問いに対する答えが出るわけではない。たとえば、テレビのドキュメンタリーの現場で想田監督が体験したことやフレデリック・ワイズマンの影響についての記述からは、「観察映画」という独自の発想とスタイルが形成される背景が見えてくる。だが、それは答えではない。本書は、答えが見えないからこそ、『Peace』のような作品が生まれるのだということを巧みに物語っている。
『Peace』のきっかけは、DMZ(非武装地帯)韓国国際ドキュメンタリー映画祭から、「平和と共存」をテーマにした短編を依頼されたことだった。観察映画は予めテーマを決めたりせずに対象と向き合うことを前提にしているので、想田監督は抵抗を覚える。だが、義父が面倒を見ている野良猫たちを見て気が変わる。そこで猫社会を描く短編という構想が生まれる。
しかしやがて、猫社会から「福祉有償運送」をライフワークにする義父・柏木寿夫に関心が広がり、彼が運ぶ高齢者や障害者の人たちと接するようになる。そのうちに、末期の肺がんを患い、在宅でホスピス・ケアを受ける橋本至郎さんに興味を引かれるようになったと思ったら、義母が「共助グループ喫茶去」を通じてその橋本さんの生活支援を行っていることがわかる。
そんなふうにしてテーマに縛られることなく対象が広がり、短編のはずがいつしか長編になっていく。最初から見えていたものなどなにもない。だが、そんな製作過程のなかでひとつだけブレないものがある。撮影中には様々な雑念が頭の中を去来するが、それを消し去るのが「観察」だという。筆者が注目したいのは以下のような記述だ。
なぜ観察が雑念を消すのに有効なのか。
僕は心理学者ではないので、学問的に確かなことは言えないが、たぶんそれは、撮影者の意識を「過去」でも「未来」でもなく、「いま」に降ろすことに役立つからだ。
例えば、「さっきピントがずれて失敗した、ちくしょう」なんていうのは、過去に意識が囚われていることを意味する。過去はすでに起きたことであり、いまさジタバタしても、決して取り返すことはできない。それなのに、くよくよと過去の失敗を悔いることで、「いま」の意識が汚染され、更なる失敗を呼ぶ。
逆に「ああしたい、こうしたい、このシーン、使えるかな?」などというのは、未来に意識が囚われていることを意味する。未来はまだ起きていないのに、そのことばかりを気にかけることで、「いま」を台無しにする。
しかし、目の前の現実を観察しようとすると、意識は「いま」に降りてくる。「いま」に意識を降ろせば、過去への後悔も未来への不安も、霧のように消えてしまう。
この「いま」という言葉は「瞬間」に置き換えられる。筆者が人間と動物をめぐる「瞬間」の意味に深い関心を持っていることは、読書日記の『祝祭性と狂気』渡辺哲夫や『哲学者とオオカミ』マーク・ローランズ、ラース・フォン・トリアー『アンチクライスト』レビューや内田伸輝『ふゆの獣』レビューなどを読めば、おわかりいただけるだろう。
渡辺哲夫は『祝祭性と狂気』のなかで、ニーチェのこんな言葉を引用している。かなり長いし、よく知られた文章なので、雑誌などではとても引用できないが、ブログなら許されるだろう。
君のそばを草を喰らいながら通り過ぎる畜群を考察し給え。彼らは昨日が何であり、今日が何であるかを知らず、跳び廻り、食い、眠り、消化し、再び跳び、かくして朝から晩まで、毎日毎日、彼らの快と不快に短く、すなわち瞬間の杭にしばりつけられて、それゆえに憂愁も倦厭も知らずに過ごす。これを見るのは人間には辛いことである。なぜなら人間は動物の前で、われこそは人間なりと胸を張ってみせているのに、動物の幸福に嫉妬の眼を向けているからである――まことに、人間がただ一つ欲していることは、動物と等しく倦厭もなく苦痛も伴わずに生きることであるが、しかし徒にこれを欲するのみである、なぜなら人間は動物のごとくこれを欲することができないからである。なぜ君は私に君の幸福について語らず、ただ私をじっと視るだけなのか?と人間が動物に仮に問うたとする。動物は答えのつもりでこう言うだろう。それは、私は言おうと欲したことをいつでもすぐ忘れてしまうからだ、と――だがそのとき動物はこの答えをまたすぐ忘れて黙り込んでしまう。だからこそ人間は動物を不思議に思うのである。
しかし人間は忘却を学びえず絶えず過ぎ去ったものに固執している自分自身についてもいぶかしく思う。彼がこんなに遠くまで、どんなに速く走っても、過去の鎖も一緒に走って来る。瞬間は忽ちにして来たり、忽ちにして去るのに、以前にも虚無、以後にも虚無であるのに、なおも幻影として再び来たり、次の瞬間の安らいを妨げる。これは実に驚くべきことである。……動物は直ちに忘れ、あらゆる瞬間が現実に死に、霧と夜のなかに沈み込み、永遠に消え失せるのを見る。動物はかくして非歴史的に生きる。
……一切の過去を忘却して瞬間の敷居に腰をおろすことの可能でない者、勝利の女神のごとく目まいも恐れもなく一点に立つ能力のない者は幸福の何たるかを決して知らぬであろうし、なお悪いことには、他の人々を幸福ならしめることを何もなさないであろう。
そして、想田監督の『Peace』を観たときに筆者が真っ先に思い出したのが、マーク・ローランズの『哲学者とオオカミ』だった。詳しくは読書日記を参照していただきたいが、哲学者のローランズは本書で、オオカミと暮らした経験をもとに、人間とはなにかを掘り下げている。サルを人間が持つ傾向のメタファーとして使い、オオカミとの違いを以下のように書いている。
オオカミはそれぞれの瞬間をそのままに受け取る。これこそが、わたしたちサルがとてもむずかしいと感じることだ。わたしたちにとっては、それぞれの瞬間は無限に前後に移動している。それぞれの瞬間の意義は、他の瞬間との関係によって決まるし、瞬間の内容は、これら他の瞬間によって救いようがないほど汚されている。わたしたちは時間の動物だが、オオカミは瞬間の動物だ。
想田監督は、「くよくよと過去の失敗を悔いることで、「いま」の意識が汚染され」と書き、ローランズは「瞬間の内容は、これら他の瞬間によって救いようがないほど汚されている」と書いている。現代では、瞬間が過去と未来、前後関係にがんじがらめにされ、瞬間の意味が見失われている。極端にいえば、生きていることや存在していることが見失われている。
想田監督の「観察映画」が私たちを引きつけるのは、そこに過去や未来、他の瞬間に汚染されていない「瞬間」があるからだろう。しかも、特にこの『Peace』という映画の場合には、登場する野良猫たちも、想田監督の義父も義母も、橋本さんもみな瞬間を受け入れているように見える。その姿は、先ほど引用したニーチェの文章の最後の部分を思い出させる。
……一切の過去を忘却して瞬間の敷居に腰をおろすことの可能でない者、勝利の女神のごとく目まいも恐れもなく一点に立つ能力のない者は幸福の何たるかを決して知らぬであろうし、なお悪いことには、他の人々を幸福ならしめることを何もなさないであろう。
●amazon.co.jpへ