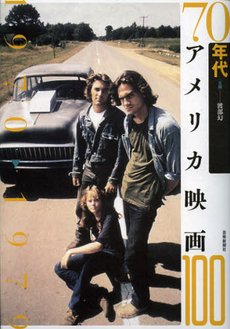『サバービアの憂鬱』と杉江さんや川出さんの『サバービアとミステリ』とジョン・カッツのサバービア探偵シリーズのこと

拙著『サバービアの憂鬱』が角川新書の一冊として復刊されることについては前の記事でお知らせした。その新書版のあとがきを書き終えたあとで、思い出していたのが、もうだいぶ前に杉江松恋さんのご厚意で拝読させていただいた『サバービアとミステリ 郊外/都市/犯罪の文学』のことだった。
この電子書籍は、杉江さん、川出正樹さん、霜月蒼さん、米光一成さんが、ミステリをコミュニティの動態を描いた小説という観点から眺めてみることに挑戦した座談会を収録したもので、『サバービアの憂鬱』がその参考書として取り上げられていた。
『サバービアの憂鬱』の視点を応用して、ミステリの作家や作品の世界を多面的に読み解いていくアプローチは刺激的だった(もっと個人的なことをいえば、筆者がその昔、ロス・マクドナルドや横溝正史を好んで読んでいた理由も説明されているようで興味深かった)。
この『サバービアとミステリ』の冒頭には、杉江さんの以下のような発言がある。
「この『サバービアの憂鬱』には、1940 年代後半からのアメリカ社会の動きが書かれていて、巻末に各章で採り上げられた参考図書のリストがあるんですね。しかし、われわれとしては意外なことに、その中にはミステリがほとんど入っていないんです。音楽、映画、一般文芸など様々なサブカルチャーには言及しているのにミステリについては全くない。これは、もしかすると『サバービアの憂鬱』では語られなかった要素が、ミステリについて触れることによって見えてくるんじゃないかという期待があるわけです。そうした形で『サバービアの憂鬱』になかった視点を補うということが一つの目標でもあります」
ブログの前の記事では、「新書版あとがきでは、本書出版後に公開されたサバービア映画から、本書の内容とつながりのあるものをピックアップし、出版以後についてもいくらかフォローしました」と書いたが、実はミステリも1本、取り上げている。ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』だ。ただ、必ずしもミステリを意識したわけではなく、この小説には、『サバービアの憂鬱』の第21章「サバーブズからエッジ・シティへ」や第22章「新しいフロンティアのリアリティ」のその先にある世界が描かれているので、外せなかった。
結果的に、新書版にはミステリもわずかながら盛り込まれることになったが、あとがきを書き終えて『サバービアとミステリ』のことを思い出したのには、別のきっかけもある。
アメリカのジャーナリスト/作家のジョン・カッツについては、ビジネス・サスペンスの『ネットワーク乗っ取り計画』やノンフィクションの『ギークス GEEKS――ビル・ゲイツの子供たち』くらいしか邦訳がないので、あまり知られていないと思うが、そのカッツは、『サバービアの憂鬱』が出版された93年から、サバービア探偵(suburban detective)を主人公にしたミステリ・シリーズを書き出した。
筆者は当時、そのシリーズに関心を持ち、ペーパーバックが出るたび購入していたのだが、もうずいぶん昔のことですっかり忘れていた。そのペーパーバックはまだどこかにあるはずだが、見つけ出せなかった。
もう記憶がかなり曖昧になっているが、主人公のクリストファー・“キット”・デリウーは、以前はウォール街で働いていたが、インサイダー取引をめぐるトラブルに巻き込まれて職を失った。彼は、ニュージャージー州のルーシャンボーという架空の郊外の町に妻子と暮らしていて、地元のショッピングモールのなかに小さな事務所を開いて、サバービア探偵になった。
1作目の『Death by Station Wagon』(1993)では、地元の高校の人気者だったカップルの遺体が発見され、警察は少年が少女を殺害した後に自殺したと判断するが、少年の仲間たちはそれに納得できず、探偵キットが捜査に乗り出す。第2作の『The Family Stalker』(1994)では、キットがある女性を追っていく。最初はよくある不倫の調査に思えるが、その女性が郊外の主婦たちと親しくなり、密かに彼女たちの夫を誘惑し、家庭を破壊している疑惑が浮上する。
その後、このシリーズは、『The Last Housewife』(1995)、『The Father’s Club』(1996)、『Death Raw』(1998)と続き、5作で終了してしまった。サバービアとミステリを結びつけるというこのシリーズの発想は悪くなかったと思う。ウォール街でのトラブルからサバービアのショッピングモールへ、という展開も80年代から90年代への流れを感じるし、インターネットや携帯が普及する以前の、モールを中心としたサバービアの日常もリアルに描かれていたような気がする。
著者であるカッツの関心が、90年代末頃から愛犬や犬とオーナーの関係に移ってしまったようなので仕方がないが、このサバービア探偵のアイデアはもったいなかったと思う。